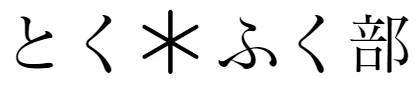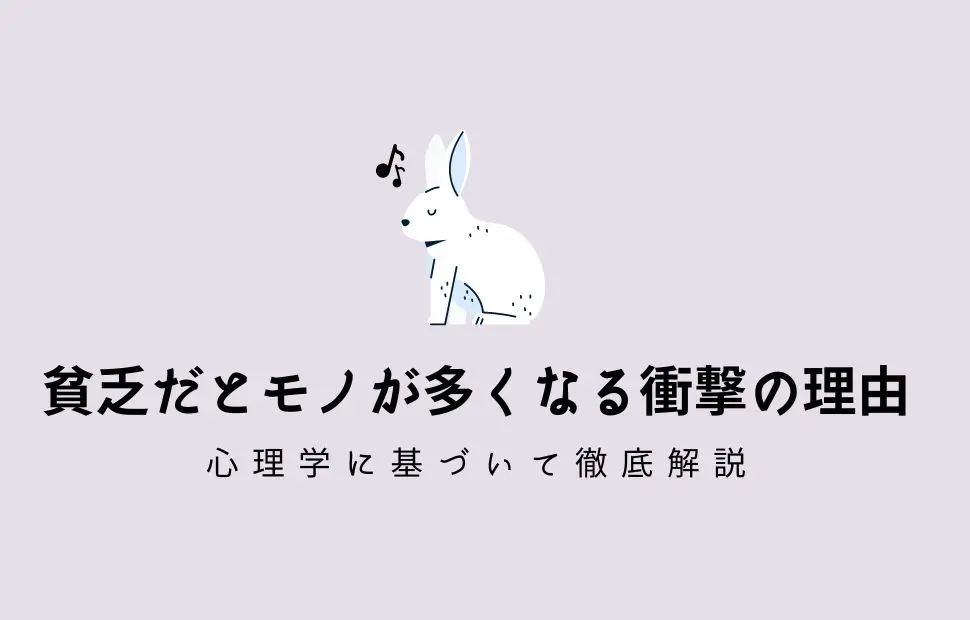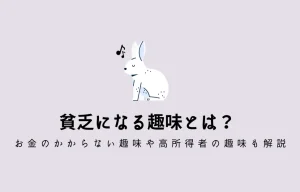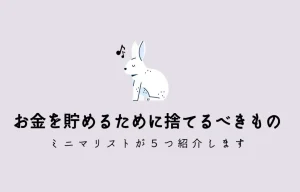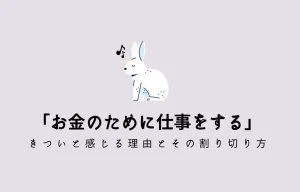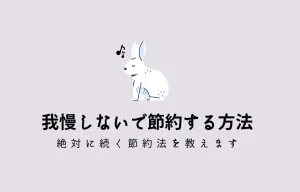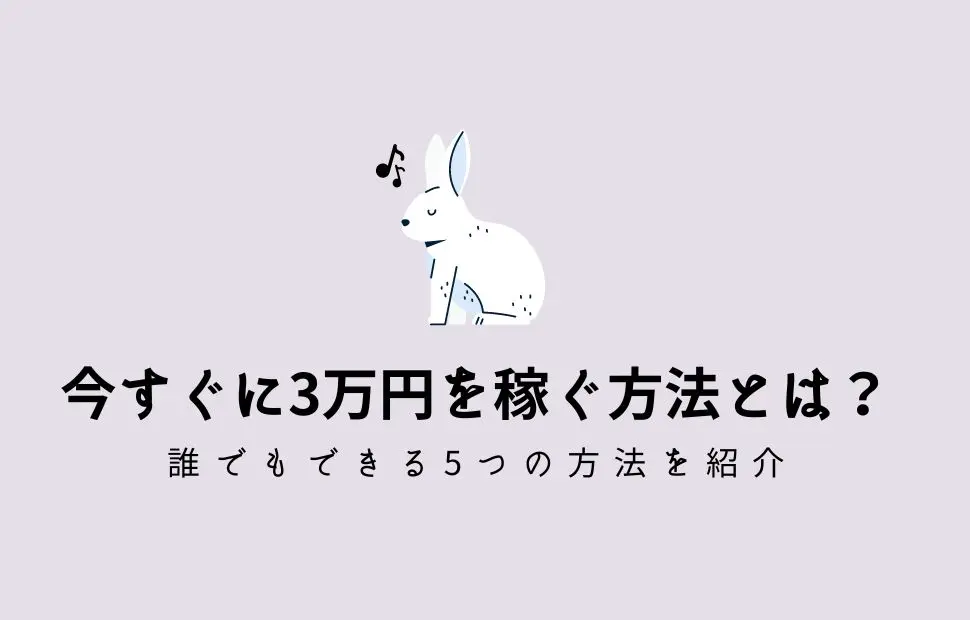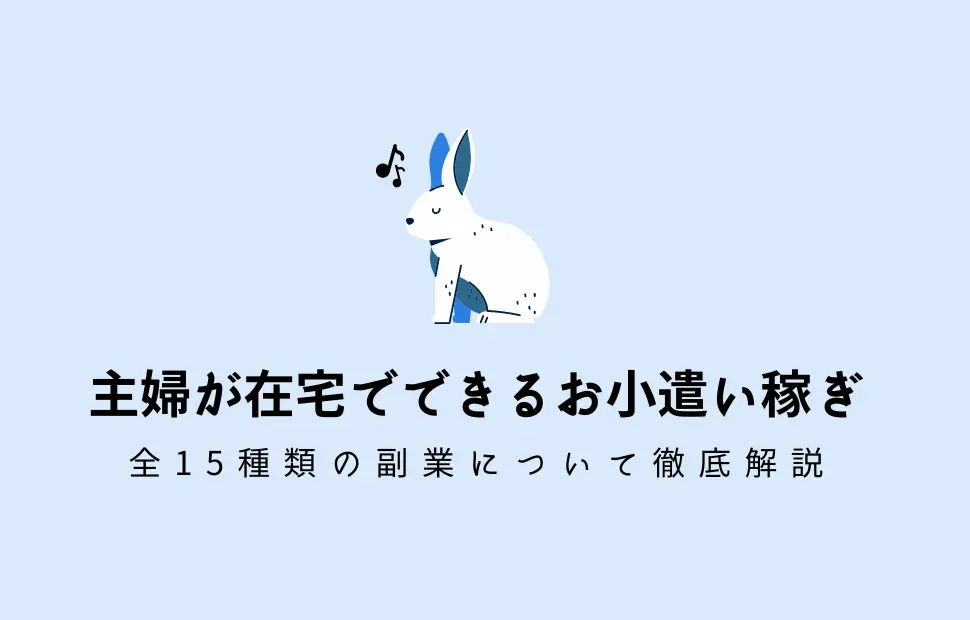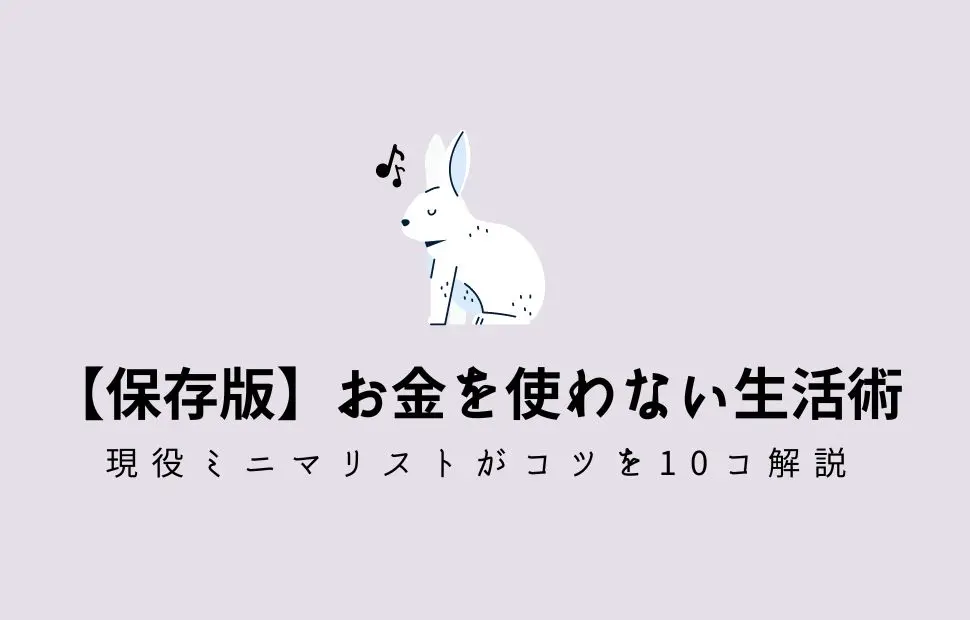ドラマや映画で「貧乏人の家ほどものが多く、お金持ちの住居はきれいでシンプル」。そんな描写をみたことはありませんか?
実はその表現は科学的にも的を得ており、実際貧乏人ほどものが多く、家が散らかっている傾向にあります。
本記事では貧乏人ほどものが多いという心理的な根拠とそこから抜け出す方法について解説していきます。
ぜひ最後までお付き合いください。
✔ 本記事の内容
参考文献については記事最下部にあるので興味がある人はぜひご覧ください。
貧困だとものを持ちすぎてしまう心理的な理由

それではさっそくお金がない人ほどモノを持ちすぎてしまう心理的な背景を3つ解説します。
①「ものを持つこと」で幸福感を得ている
貧困状態の人は、生活費が限られているため、物を持つことが一番の贅沢になっていることがあります。
少ない予算で効果的に満足感を得るため、安価なモノでも手に入れることが魅力的に映るのです。
ただ、安いものばかり買っていると満足感を得られず次に消費へとつながってしまい、結果的にさらにお金がなくなっていきます。
しかも、安いものは長持ちしないことが多く家にはガラクタが増えるばかり‥
 ゆるめ
ゆるめ「安物買いの銭失い」とはよく言ったものですね。
何かものを買う際は質の良く、本当に必要な分だけ買うのが長期的に見てもっとも節約になりますよ。
②安心感をもので補う
お金がないと将来の不安や経済的な不安定さを感じることが多いですよね。
こうした不安を和らげるため、物を持つことで少しでも安心感を得ようとする動機が働くことがあります。
モノを買うことで一時的に不安から逃れているんですね。本質的にはお酒と同じかも・・
③劣等感が消費を加速させてしまう
貧困な状況にある人々は、周囲の人々と比較すると、物質的な面で劣っていると感じることがあります。
こうした比較が、物を持つことの重要性を高めてしまうのです。
逆にお金に余裕があれば、他人と自分を過度に比較することをやめ、自分にとって本当に必要なもの・本当に欲しいものを購入することができます。
見栄を張るためにブランド品を購入してしまうのも劣等感が消費を加速させている良い例ですね。
モノが多い生活と貧困から抜け出す方法

貧困だとモノが増えてしまう理由はわかりましたが、モノが多い生活と貧困から抜け出すにはどうすればいいのでしょうか?
ここではモノが多い生活と貧困から抜け出す方法を具体的に4つ解説します。
- 自己管理能力を身に着ける
- 徹底的にモノを減らす
- 他人と比較することをやめる
- 「経験」にお金を使う
①自己管理能力を身に着ける
実は自己管理能力の高さと学業成績・人間関係の健全さ・経済力は比例することが明らかになっています。
考えてみれば、自分の感情をコントロールして努力できる人の方が成功しやすいのは明らかですよね。
ではこの「自己管理能力」を身に着けるにはどうすればいいのでしょうか?
自分を思い通りに動かす方法は多岐にわたりますが、もっとも大切なのは心身の健康を保つことです。
以下の本では95に及ぶセルフコントロール法が紹介されているのでぜひご覧ください。
②徹底的にモノを減らす
モノを減らしたいならまず思い切って断捨離しましょう。
生活から不必要な選択肢を取り除くことにより、ストレスが取り除かれ精神的な余裕もできます。
モノが多いと、選択肢が増えてしまいストレスが増え、決断力が鈍くなってしまいます(ジャムの法則)
さらに掃除の手間やモノ探しの手間が増えることで余計な時間を使うことにもなってしまいます。
 ゆるめ
ゆるめシンプルでストレスが少ない生活にするためにも断捨離は必須ですよ。
断捨離のコツはこちらの記事がとてもわかりやすくおすすめです。
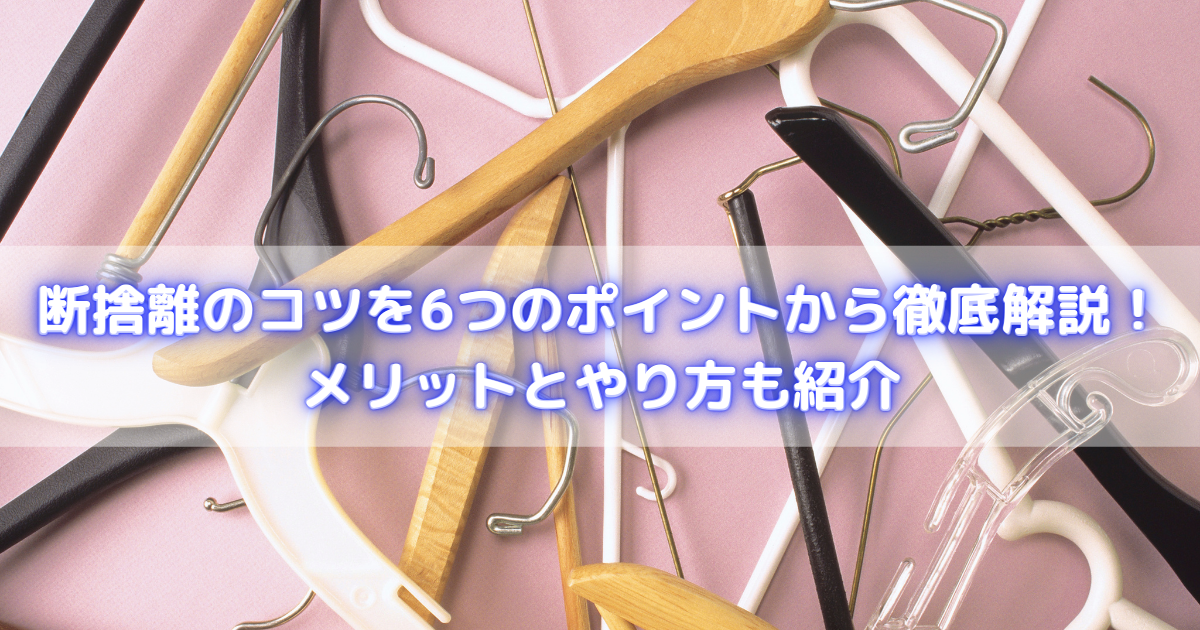
③他人と比較することをやめる
SNSが浸透している現代で他人と比較せず自分らしく生きることはかなり難しいです。
しかし、他人と比較することで生まれた劣等感は見栄や安心感のためにモノを消費することにつながります。
他人と比較しすぎず、主体的な生き方ができるようになれば精神的な余裕ができ、余計なモノを買うこともなくなるでしょう。
④「経験」にお金を使う
モノばかりにお金を使っていては貧乏から抜け出すことはできません。
旅行や英会話教室・スクールなどもっと経験にお金を使うようにしましょう。
経験にお金を使うことでスキルや資格を得たり、考え方や人生観に大きな影響を与えることができます。
 ゆるめ
ゆるめものは一時的な資産ですが、経験は一生の資産になりますよ。
最後に
いかがだったでしょうか?
本記事ではお金がない人ほど物を多く持つ背景やそこから抜け出す方法について解説しました。
本メディアでは主にブログ運営・副業・お金に関する知識を中心に発信しています。
収入をUPさせるのに一役買う記事がいくつもあるのでぜひご覧ください。